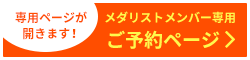前回、今の国の施策は育児系に向いていて、高齢者系は薄くなり始めている旨を書きましたが、今回は、これに関連する児童手当法の改正と、その計算方法について記したいと思います。
1.児童手当の支給要件から「所得要件」が削除されました。
2.児童手当は、月を単位として支給され、その支給対象となるのは、児童手当法の児童、すなわち、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、所定の者をいいます。
3.児童手当の額は次の表のとおりです。
| 支給対象児童 | 児童手当の1人当たりの月額 |
| 3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
| 3歳以上18歳年度末まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
↓
支給期間がこれまでの15歳年度末から18歳年度末まで延長されました。
- 「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をいいます。以下同じ。) のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます
↓
「第3子以降」のカウント対象の年齢がこれまでの18歳年度末から22歳年度末まで延長されます。 (子供が3人以上いる場合に必ずしも「第3子以降」としてカウントされるわけではありません。 児童の兄姉等については監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している必要があります)
5.実際の計算
(例1)21歳、12歳、5歳の子がいる場合
第1子0円+第2子10,000円+第3子30,000円=40,000円
(例2)24歳、20歳、15歳の子がいる場合
24歳の子はカウントしない。第1子0円+第2子10,000円=10,000円
実際に自分で計算してみると、すぐに覚えられると思います。