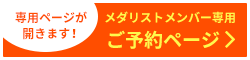社労士試験の受験生を悩ます科目のひとつに「一般常識」があります。「一般常識」という科目ですが、ちっとも「一般的な常識」ではありません。わけがわからないことばかりです。
ボクは受験生のとき、一般常識は「法令」に特化して学習しました。労働経済や社会保障制度など「厚生労働白書」や「労働経済白書」、「その他各種統計」のどこから出題されるか、全く予測不能だったからです。
だったら確実に出題される法令を完璧に覚えて、最低ラインを超えてしまおう。
そんな気持ちになりました。
結局選択問題は全問正解、択一式問題は5問正解で足切りにならなかったことを覚えています。
では、一般常識の法令について、どの法律が出題されやすいのでしょうか。見ていきたいと思います。
- 労働関連の法律から
まず過去確実に出題されているのが労働契約法です。労働契約法はたった20条しかない法律ですから、絶対に落とすことのできない科目です。絶対に完璧にしておく必要があります。
次に労働組合法についても過去10年に8回出題されています。これも完璧にしておかなければならない法律です。
あとは男女雇用機会均等法、障害者雇用促進法、最低賃金法が割と出題されやすい法律でしょうか。
- 社会保険関連の法律から
どの法律も満遍なく出題されていますが、まずは国民健康保険法と社会保険労務士法、高齢者の医療の確保に関する法律は、ほぼ毎年出題されているといっていいでしょう。
その他出題されやすい法律は、介護保険法、児童手当法、確定拠出年金法か確定給付型企業年金法のいずれか、といったところでしょうか。今年は確定拠出年金法の法改正があったので、こちらの方が出題の可能性が高いようにも思いますが。
いずれにせよ労働経済と社会保障制度については、毎年出題されているところです。特に労働経済については、選択式問題で出題される傾向が高いと言えます。
正直、これが合否のカギを握る問題にならないことを祈るばかりです。